
【前編】明治大学が和泉ラーニングスクエアで目指したものとは
2020年に創立140周年を迎え、多くの優秀な人材を輩出し続ける明治大学。
その明治大学が、新しい時代の、新しいキャンパスのあり方を模索した結果、導き出された一つの答えが、和泉キャンパスに新たに誕生した教育棟「和泉ラーニングスクエア」です

今回は最先端のラーニングコモンズを核とするアクティブラーニングを実現しつつ、明治大学の教育プログラムや学生のニーズとも整合性を持たせた空間づくりをどのようにしておこなったのか。
プロジェクトを担当した学校法人明治大学 管財部施設課 菅和禎課長補佐へ詳しくお話を伺いました。
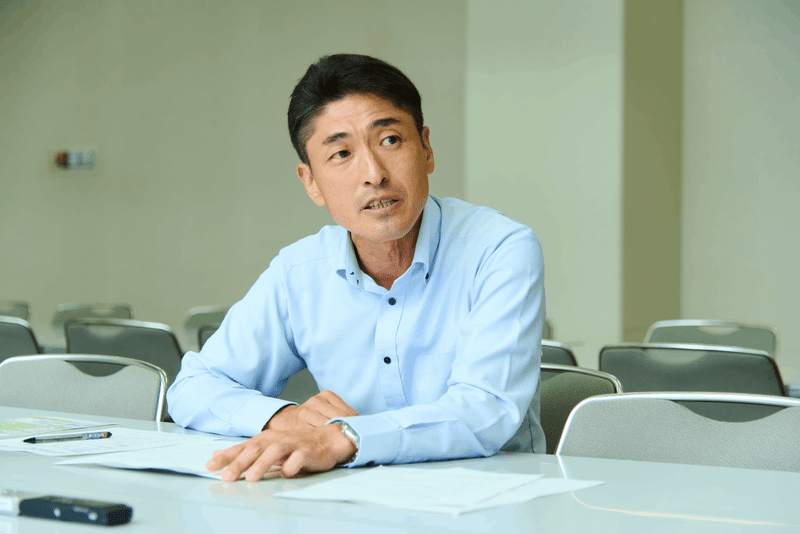
和泉ラーニングスクエアとは?
和泉ラーニングスクエアとは、明治大学和泉キャンパスに新たに誕生した教育棟です。
日本近代建築100選にも名を連ねる明治大学建築学科創設者の 堀口捨己先生が設計した第二校舎の建て替えにより建設されました。
7階建ての校舎はラーニングコモンズを核とするアクティブラーニングを実現するための様々な工夫が随所に配されており、また2F、4F、6Fのブリッジでメディア棟と、3Fのブリッジで和泉の杜(食堂棟)ともつながることで、ハブとしての役割も果たしています。

これまで抱えていた問題
歴史のある明治大学だけに、伝統を大切にしながらも現代の教育にマッチした環境にアップデートをしなければならならないという難しい問題を抱えていました。
建物の老朽化 バリアフリーの不備
明大生であれば誰もが記憶に刻まれている第二校舎は1960年竣工。
60年以上の時が過ぎ、建物の老朽化が問題となっていました。
またバリアフリーの不備も喫緊の課題となっていたのです。
教室数不足 メディア棟の混雑
教室数の不足も問題となっていました。
特にPCの使用やオンライン授業が当たり前となった現在、各教室にマルチメディア機器を備えたメディア棟に利用が集中し、混雑してしまうことが常態化していたのです。
大型モニターやカメラを備えた教室や、Wi-Fi、PC用電源を完備したキャンパスの整備は待ったなしの状況となっていました。


明治大学が和泉ラーニングスクエアで目指したもの
明治大学が和泉ラーニングスクエアで目指したのは、近年の社会の激しい変化に対応し、総合的な知の地盤である「教養教育」を展開する場を創出することでした。
そして明治大学が、時代に適した「新しい教育」を提供する大学であることを世の中に発信する。
この時代におけるキャンパスの価値を再定義したいと考え、「キャンパス=教材」として、
『いま、一番必要な教材はキャンパスだと思う。』
というキャッチフレーズを掲げたのには、そのような思いが込められていたのです。
和泉ラーニングスクエアは「箱」
大切なのはそこで何をどう学ぶか!
上記した目的を達成するためには、まず単なる従来の教室棟の建て替えではなく、今の時代に必要とされる新しい学修環境を展開する新たな教室棟、新たな学びの空間を付け加えた教室棟を作ることが必要でした。
ただそのような教室棟=和泉ラーニングスクエアを建設してもそれはあくまでも入れ物、箱に過ぎません。
明治大学は和泉ラーニングスクエアの完成自体を目的としてはならず、ラーニングスクエアに込められた意味や意志に焦点を当てる必要があると考えたのです。
それはラーニングコモンズを核とするアクティブラーニング、受動的な学びから学生の主体的・対話的な学びへの変革という新しい学修スタイルの確立でした。

主体的・対話的な学修スタイルを確立するためには「学生が集まる」ことが大前提
ただラーニングコモンズを核とするアクティブラーニングを実現し、主体的・対話的な学修スタイルを確立するためには、学生がラーニングスクエアという「場」に集まらないと話になりません。
そこで明治大学が考えたのは『学生が集まる場所を作ろう』ということでした。

学生が集まる場所を作るためには
空間を演出し、魅力的なものにする必要があった
学生が集まる場所を作るためには、その空間に工夫をこらした演出を加え、学生を惹き付ける魅力的なものにする必要があります。
そこで明治大学は、学生がどのような行動をとり、どのような傾向があるのかということについて、綿密なリサーチをおこないました。
綿密なリサーチで分かった、学生は
「スタイリッシュ」「にぎやか」「飲食可能」
な空間に集まる
リサーチのモデルとなったのは2012年に竣工した同じキャンパス内の和泉図書館や食堂、中庭といった学内施設。
図書館でありながら内部にカフェ、共同閲覧室、グループ閲覧室を有し、利用者のための多様な空間を提供する和泉図書館は、アクティブラーニングのリサーチの場としてはうってつけだったのです。

そこで分かったことは、
学生は4~6人のグル-プで行動する
スタイリッシュな空間に惹きつけられる
静か過ぎず、賑わい過ぎない空間
飲食可能で友達と相談しながら勉強できる所は人気が高い
といったところでした。
このリサーチを元に、和泉ラーニングスクエアのコンセプトが固まっていきます。

スタイリッシュでありながら
馴染みやすく、居心地の良い空間作り
『学生がいつでも気軽に来たくなる、馴染みやすい空間』
和泉キャンパスは1、2年生のキャンパスであることから、比較的カジュアルな建物とし、学生が親しみやすい空間をつくろうと考えられました。
例えば和泉ラーニングスクエアの建物内には1~3階、4~7階に吹抜けがあります。
明治大学ではこの吹き抜け部分の空間を一つの広場として捉え、少人数で多目的に利用できるガラス張りのグループボックスや、スタイリッシュなカウンターを設置。

学生が集まりやすい仕掛けを作っています。
またインテリアについても、靴を脱いで横たわったり、中にこもったりすることができる家具ボックスややぐらを配置し、「そこに行ってみたい!」と学生に思わせるようになっています。

『「こんなスタイリッシュな場所で勉強できるのか!」と思える空間』
和泉ラーニングスクエアを利用するのは大学1、2年生が中心。
少し背伸びをしたい大人になりかけの年代なので、スタイリッシュな家具やデザインを用い、「あそこで勉強していたらかっこいいな」と思わせるようにしています。
取材日は入学式から少し経った4月中旬でしたが、建物内には自然と学生が集まり、いろいろな場所でいろいろな活動をしている学生の姿であふれていました。
特にエントランスホールである1階から3階の吹抜け部分にはガラス張りのグループボックスを設置。
各グループボックスはそれぞれがカラフルなカラーで色分けされており、ガラス張りのため中で学修活動をしている学生の姿を外部から見ることができます。

海外から取り寄せたデザイン性の高いインテリアも配置されたその空間は、まるで公開スタジオのようであり、学生が主役となって見る見られる関係を意識させ、お互いに学修意欲をかきたてるような仕掛けになっているのです。
『リビングやカフェのように居心地が良く、長く滞在できる空間』
学生の多様性に配慮した、多種多様な場を作り上げているのも印象的です。
アクティブラーニングを意識した、いろいろな場所でいろいろな事ができるような空間作り。
学生がその日の人数や学修内容によっていきたい場所を選択できるようになっています。
共用部にはみんなが集まれる交流スペースや、グループから個人で利用できる学修スペースが用意されており、そこでは飲食も可能。

全体的に自然光を取り入れた明るく快適な空間となっており、グリーンテラスと呼ばれる半屋外空間のテラスもあったりして、まるで居心地の良いリビングやカフェのような雰囲気でした。
たくさんの友人という財産を
明治大学でたくさん作って欲しい
菅様にお話をうかがうと、
「学修することはもちろん重要だが、大学時代の友人は長い付き合いができる大切な財産。
多くの人と交流し、一生涯の付き合いとなる友人をたくさん作ってほしい」
とのことでした。
そういった意味でも和泉ラーニングスクエアは様々な学生の様々な活動を想定しており、コラボも生まれやすく、偶然の出会いが生まれやすくなっています。

学生たちで賑わう1~3階の吹き抜けホールは、そう感じさせるのに十分なものでした。
後編へ続く
後編では主体的・対話的な学修スタイルを確立するために学生を集め、多種多様な利用方法を提供する和泉ラーニングスクエアの各パートについて、詳しくお伝えしてまいります。
学校施設の事例集はこちらから!

今の課題をなんでもご相談ください!

はじめてのオフィス移転もこれで安心!

清和ビジネスの環境構築ソリューション事例

